試用期間とは|求人情報や労働条件通知書への記載や解雇のルールについて
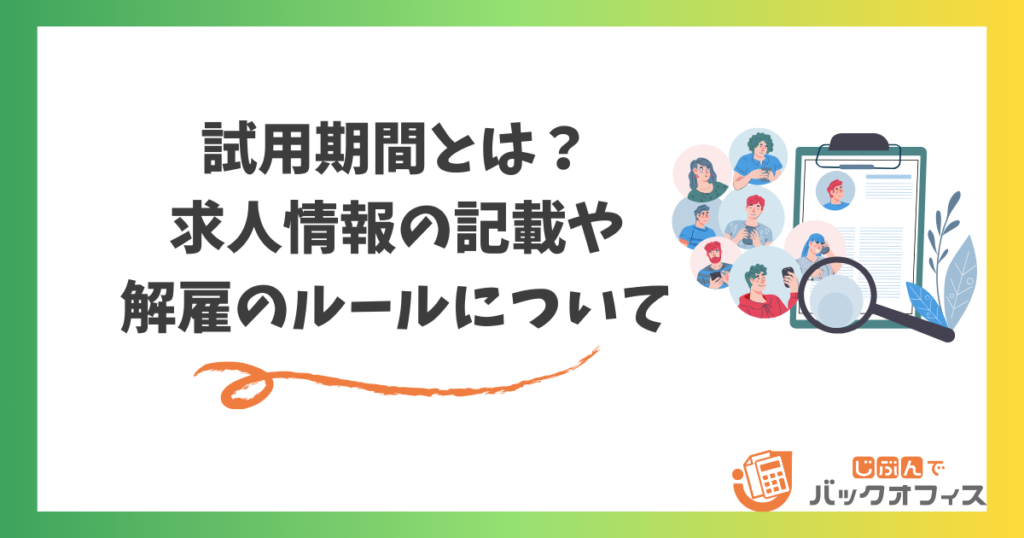
労働者の募集、そして何度かの採用面接を終え、いざ労働契約を締結するとなったときに、応募者側から試用期間に関して質問を受けることがあるかもしれません。
個人事業主が雇用をするときでも試用期間を定めることは可能です。ただ、法律上のルールには注意が必要です。「お試し期間だから」と軽く考えていると、労使トラブルに発展してしまう可能性があるのです。
この記事では、試用期間について、採用前の求人票の記載から正式採用以降のことまで、従業員を雇用しようとする個人事業主が知っておくべき法律やルールを解説をしています。「試用期間」の設定について検討している場合は、確認しておきましょう。
試用期間とは?
従業員を雇用するとき、正式な採用の前にその者の適性を見極める「試用期間」を設けることができます。
もちろん、そういった期間を設けずにそのまま正式な採用としての手続きも可能で、法律上の問題も生じません。
しかし、雇用した者の能力の実態や勤務態度は、履歴書や採用面接だけでは判断が難しいです。そこで、多くの事業者が試用期間を定めています。
試用期間中は解約権留保付労働契約が成立している
試用期間中は「雇用主側が労働契約を解約する権利を留保している状態」です。
通常の解雇とは違い、就業規則に定められている解雇事由に必ずしも制約されません。採用した者が従業員として不適格と判断された場合に、労働契約の解約が雇用主側に留保されているという特別な状況下にあるのです。
反対に言えば、雇入れ当初より正式採用、または試用期間が終了して正式に雇用されたとき、極端に勤務態度が悪い・虚偽の申告により採用されたといった、よほどの理由がなければ解雇はできません。
一方、雇用される側の立場から見ると、従業員としての立場が確立されていない不安定な地位にあると言えます。
試用期間を設ける場合のルール
期間中の労働条件の記載方法やその長さにはルールがあり、全てを自由に決めることはできません。
また、労働契約が成立している状態に変わりはありませんので、有給休暇や社会保険は雇入れ当初より適用されます。この点は通常に働いている従業員と変わりはありません。
その他、期間中の賃金やボーナスの査定など、正式な採用となった後との差についてよく疑問とされる点について以下にまとめましたので、確認しましょう。
試用期間の長さ
「試用期間の長さ」については、法律による制限がありません。
ですので、原則事業主などが労働条件通知書や就業規則に根拠を規定することで、自由に定めることができます。
しかし、その期間働くことは労働者の立場では、本採用ではない不安定な状況です。そのため、あまりに長い期間(1年以上)に及ぶと、労働者をその間安定しない地位に留めるため、不適切と考えられています。
標準は大体「1ヶ月~6ヶ月」の期間です。
期間の長さを決めるときの基準として、採用予定の従業員の雇用の形態(無期正社員、有期契約社員、アルバイトなど)を参考にするとよいでしょう。例えば、無期雇用の正社員の場合は、少し長めに適正を判断したいから6ヶ月、というように考えることができます。
また、やむを得ず期間を延長したい場合でも、どちらかが一方的に行うことはできませんので注意しましょう。
試用期間中の賃金
試用期間中に正式採用後と賃金差をつけること自体は違法ではありませんが、労働条件通知書や就業規則などに根拠となる規定が必須です。規定を定めている場合は、きちんと相手に説明をしましょう。
また、試用期間中の賃金に差が認められているとはいえ、地域の最低賃金を下回る設定をしてはいけません。
法律では、試用期間中の者の賃金を最低賃金以下に減額できる特例がありますが、それには合理的な理由が求められます。そのうえで、労働基準監督署を通じて労働局へ申請し、許可を得て認められます。簡単にできることではありませんので、気をつけましょう。
求人情報への記載
職業安定法の改正により、平成30年から求人票には、試用期間の有無や長さについて記載が義務づけられています。そのため、従業員を募集しようと思う前から、事業主側の対応を決めておきましょう。
労働条件通知書や就業規則への記載
雇用主は雇用しようとする者へ「労働条件通知書」を発行しなければなりません。また、常時10人以上の労働者がいる事業場は就業規則の作成義務があり、どちらも労働者の正式な労働条件として認められるものです。
どちらにも法律の義務として、必ず明示しなければならない「絶対的記載事項」と、定めを置くときは明示しなければならない「相対的記載事項」というものがあります。
試用期間はどちらの記載事項にも該当しません。そのため、法律上は記載が自由・任意ということです。
しかし、賃金差を設定する場合、それは「賃金に関する規定」として労働条件通知書か就業規則のどちらかに記載する必要があります。
また、同じく賃金に関わるものとして「ボーナス(賞与)の査定」があります。ボーナス自体は、与えるか与えないかも事業主の自由です。その査定に試用期間が影響するかの扱いも同様に自由ですが、査定期間に含めないのであればきちんと明示しなければなりません。
このように、試用期間自体については労働条件通知書や就業規則への記載義務はありませんが、その他の労働条件に関して、関係することがあれば記載が必要です。
試用期間を設けても解雇は自由ではない
日本の労働基準法は労働者を保護する観点から、事業主側に解雇について厳しい制限をしています。
たとえ試用期間であっても、合理的な理由に乏しく社会通念上認められづらい解雇は、権利濫用として無効となることもありますので、解雇は自由だと考えるのは危険です。
ところが、前述したように試用期間中は解約権留保付の労働契約がなされています。では、この期間中の解雇はどのように考えれば良いのでしょうか。
試用期間中の解雇
試用期間中は、通常の解雇と異なる点があります。
ひとつめは「解雇予告の期間について特例がある」という点です。
通常、従業員を解雇する場合は「解雇予告」といって、解雇通知を少なくとも解雇しようとする日の30日前に行うか、あるいは30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。しかし、試用期間中の14日以内であれば、この必要はないという特例があります。
それでも14日を過ぎた場合は、この特例は適用されませんので気をつけましょう。
ふたつめは「解雇事由が比較的広く認められる」という点です。
たとえば、書類選考や面接の過程では到底知ることができない、従業員として著しい能力不足や健康不良、経歴詐称などが理由となります。しかし、雇用主側による従業員への改善を促す対応も求められますので「なんとなくうちの会社に向かない」などの根拠の弱い理由では、解雇が無効とされることもあるので慎重さが必要です。
試用期間終了後の解雇について
期間終了後、つまり正式に採用された後の解雇は、その状況を回避するための事業主側の努力や対応があったかなどが厳しく問われ、事業主側の責任が重くなります。
また、労働条件通知書や就業規則に則った理由である必要があるため、事前の取り決めも非常に重要なことです。
当然、解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いも適用されますので、非常に難しいことだと認識しておきましょう。
試用期間を定めるメリット
上記のように、一度従業員を雇用すれば、解雇は非常に難しくなります。試用期間中は一定の制限はあるものの、選考の過程ではわからない従業員の実態を見ることができる、貴重な期間です。
特に個人事業主の場合、いざ雇い入れた従業員が、実は応募条件としていた能力に足りていなかった、ということになってしまうと事業運営に痛手となります。
あるいは試用期間を設けず、正式採用後に軽い気持ちで解雇をしてしまうと、大きな労使トラブルへの発展も考えられるでしょう。その場合、個人事業主は無限責任の下、そのトラブルを解決をしなければなりません。
ですので、試用期間には大きなメリットがあると言えます。しかし、あまり長い期間にすると、応募者からは敬遠されてしまうというデメリットにもなりますので注意しましょう。
また、反対の立場の採用される側にとっても、個人事業主の下で勤めることに不安を感じることもあります。労使がお互いに適性を判断するための期間として、有効に活用しましょう。
試用期間を定めて雇用するときの注意
試用期間を定めるかどうかは労働者を雇いたい事業主側の自由です。しかし、その期間を設けないことは、当初よりその者を正式な従業員として迎え入れることになります。
後から採用上に問題が生じても、労基法の下では事業主の責任が重く厳しい解雇制限があるため、事業運営にとって思わしくない結果もあるかもしれません。
法律やルールを守り、試用期間を適切に活用することで労使トラブルを回避し、納得のできる従業員雇用をしましょう。

